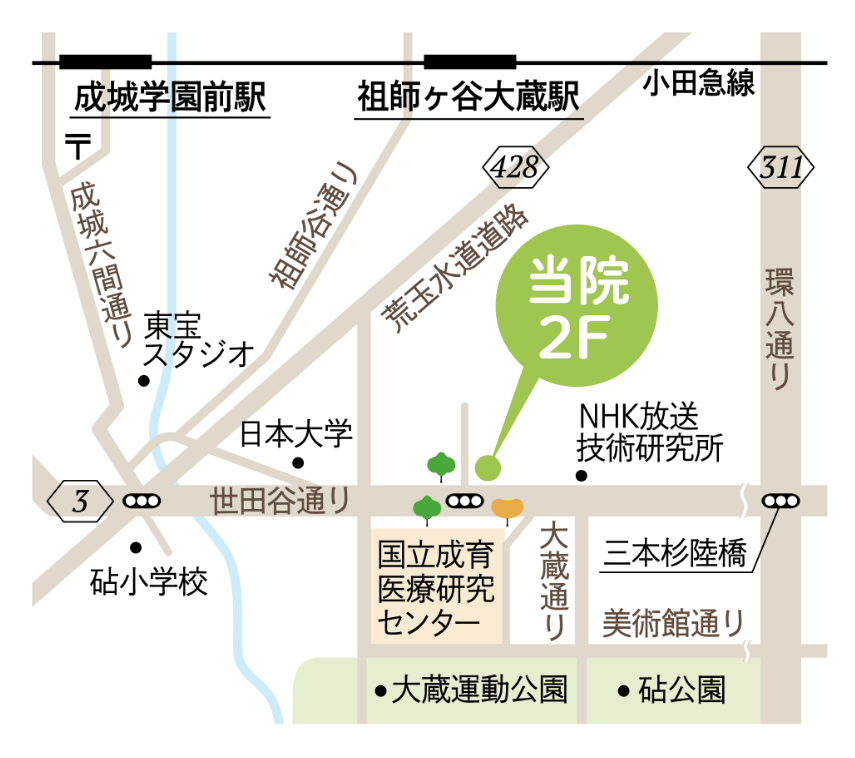頭頸部腫瘍とは

頭頸部とは、脳と目をのぞく首から上の領域を言います。
一般に頭頸部腫瘍とは耳下腺、顎下腺を含めた頸部、鼻・副鼻腔、口腔、咽頭、後頸部及び甲状腺にできる悪性腫瘍(癌)及び頸部の良性腫瘍を指します。頭頸部領域は呼吸、食事、発声など日常生活に欠かせない重要な機能が集中しており、この領域に異常が生じると日常にも大きな影響が出てくる可能性があります。
頸部でよくみられる病気
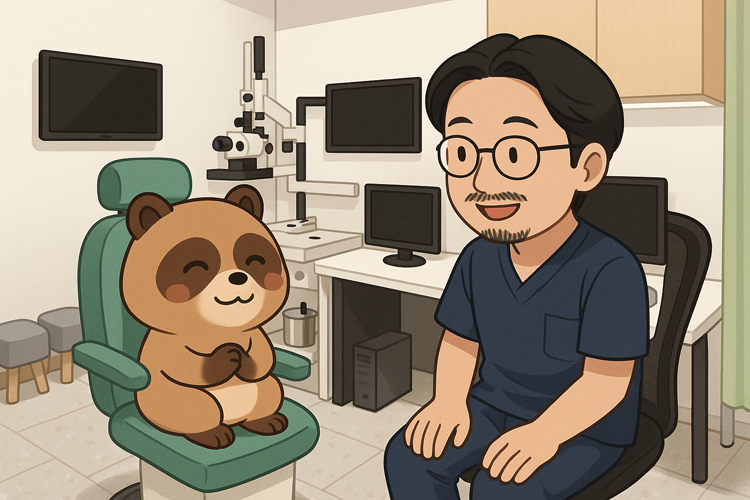
甲状腺腫瘍
甲状腺は首の前方、気管に蝶々が羽を広げたような形で付着している組織になります。
甲状腺ホルモンという活力に関わるホルモンを産生していますが、その甲状腺の内部に腫瘍を認めることを言います。
良性腫瘍(腺腫様甲状腺腫、濾胞腺腫etc)であることが多いですが、悪性腫瘍(癌:乳頭癌、濾胞癌、髄様癌、未分化癌。その他:悪性リンパ腫)であることもあり、精密検査に加え、定期的な経過フォローや加療が望ましいです。甲状腺腫瘍は女性に多いと言われており、比較的若い女性も罹患しうる腫瘍として知られます。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- 首(前頸部)が腫れてきた
- 喉の圧迫される様な違和感がある
- 声がかすれてきた
- 症状もなくエコーで偶然発見されることも多い疾患です。遺伝性(家族性)のある病態もあり家族に甲状腺の病気などある方は一度検査をすることをお勧めします
診断、治療
触診による甲状腺腫瘍の発見率は0.78〜1.87%とされますが、エコーによる評価で発見率は6.9〜31.6%となるとされます。
手術により摘出した甲状腺に偶発的に腫瘍が見つかることも多くはありますが、治療が必要なほどの甲状腺腫瘍についてはエコーでの発見が可能なため、頸部の腫脹や甲状腺疾患が気になる方は是非一度受診をいただき評価を行ってください。
甲状腺腫瘍を認める場合、また甲状腺機能異常が疑わしい場合には腫瘍マーカー、甲状腺機能等の採血評価を行い、腫瘍の形態や大きさに合わせて穿刺吸引細胞診(腫瘍に針をさし良悪性の判断を行います)などを実施します。
治療は腫瘍が良性を疑う場合、原則的には経過観察となりますが、腫瘍が大きく美容上、記になる場合や喉への圧迫感が強い場合は手術の適応となります。甲状腺がんの場合はまず手術による摘出が第一選択となります(その後の所見によりヨード治療や抗がん剤を行うケースもあります)が、大きさなどによっては厳重経過観察とする場合もあります。
耳下腺腫瘍
耳の前から耳の下にかけて耳下腺という臓器があり、唾液を産生、分泌する組織です。顔を動かす神経である顔面神経は耳下腺を貫通するように通過しています。この耳下腺から発生する腫瘍が耳下腺腫瘍で多くは良性ですが、多形腺腫という腫瘍の場合には、長い経過のうちに悪性化(癌化)してしまうケースもありその場合は悪性度も強いがんとなるため、手術による摘出が望ましいです。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- 耳の前から耳の下にかけて硬結を触れる
- 耳の前から耳の下にかけて違和感がある
- 食事をした後に耳の前から耳の下が腫れる(唾石症を疑う所見)
- 顔が動きづらい(他にも記にすべき疾患が複数あります)
診断、治療
耳下腺腫瘍が疑われる場合にはまず頸部エコーを行います(当院で実施可能です)。耳下腺腫瘍が疑わしい場合、否定できない場合はMRIによる精密検査を行い、腫瘍の性状を調べるため細胞をとって評価(細胞診)することもあります。
治療は基本的には手術加療が主となります。手術は顔面神経を保護しながら行うため、繊細な作業を要するものとなります。治療が必要と判断された場合は入院手術が可能な医療機関へ紹介させていただきます。
顎下腺腫瘍
顎下線は耳下腺に次いで人体で2番目に大きな唾液腺(唾液を分泌する腺)になります。顎下部といい顎のラインのわずかにしたあたりに左右それぞれ位置しています。
顎下線にできる腫瘍は比較的稀ではありますが、耳下腺腫瘍と比較して、顎下腺腫瘍は悪性(癌)の割合が多い(半数以上)ことが知られておりきちんと検査及び治療を行うことが必要となります。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- あごの下に硬結を触れる
- あごの下に違和感がある
- 食事をした後にあごの下が腫れる(唾石症を疑う所見)
診断、治療
顎下腺腫瘍が疑われる場合にはまず頸部エコーを行います(当院で実施可能です)。エコー上、腫瘍が疑わしい場合や腫瘍が否定できない場合はMRIによる精密検査を行い、腫瘍の性状を調べるため細胞をとって評価(細胞診)することもあります。
治療は基本的には手術加療が主となります。治療が必要と判断された場合は入院手術が可能な医療機関へ紹介させていただきます。
口腔腫瘍/口腔がん
口腔内に発生する腫瘍の総称のことで、口腔内にできる悪性腫瘍(癌)のことを口腔がんと言います。
具体的には歯肉(歯茎)や頬粘膜(ほっぺの内側)、口蓋部(口の上側の部分)、舌にできる腫瘍ですが、口腔がんのうち最も多いのは下記に説明する舌がんになります
いずれも早期発見、早期治療が重要な腫瘍なので、口の中にしこりが出来たり、なかなか治らない口内炎ができたりする場合は一度耳鼻科への受診をしてください。
進行すると口の開けにくさ(開口障害)、飲み込みにくさ、話しづらさなどが出てきますが、口腔がんで左記の様な症状が出ている場合は進行がんの可能性が高いです。
舌がん
上記、口腔がんの中で最も多いのが舌がんで、報告にもよりますが口腔がんのうち、30-60%が舌がんを言われます。
そのほとんどが舌縁部といって、舌の左右の縁にできる腫瘍になります。原因としては飲酒、喫煙に加え、歯牙との接触などによる慢性的な刺激で、60歳代以降が多いですが、一方で20-30代の比較的若い世代にもできる癌として知られています。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- 舌にできものがある
- 口内炎がなかなか治らない(2週間以上)
- 舌(特に舌の縁)に痛みを伴っている
- あごの下に硬結を触れる(顎下部周囲のリンパ節転移が多いため)
診断、治療
診断にはまず視診、触診が非常に重要です。悪性を疑う初見の場合は一部摘出し病理検査による良悪性の評価を行います。比較的早期にリンパ節転移を生じることも知られており、合わせて頸部エコーや造影CTなどによる頸部の評価、腫瘍の状況の評価のため造影MRIの検査も行っていくことになります。
治療は放射線治療の効果が乏しいことが多く、標準治療は手術を行いますが、舌は「食べること(嚥下)」「話すこと(発話)」等、機能に大きく関わる組織のため、手術による切除により大きく機能を失ってしまうこともあります。早期発見・早期治療が非常に重要ですので、例えばなかなか治りづらい口内炎や舌のしこりなどを自覚する場合には早めに耳鼻咽喉科に相談することが必要です。
喉頭がん
喉仏のあたりに喉頭はあり、喉頭は「呼吸」「飲み込み(嚥下)」「発声」に非常に重要な役割を示します。
喉頭がんは男性に多いことが知られ、60歳以上で特に多いがんです。原因は主に喫煙(一部飲酒があり、喫煙、飲酒の両方の習慣がある方は発癌リスクが高まることが知れます。)で、喫煙の原因となる癌は肺がんを思い浮かべるケースが多く、その通りなのですが、喉頭がんはよりそのリスクが高まり、非喫煙者と比較して32倍ものリスクがある事が知られています。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- 嗄声(声枯れ)が出て治らない
- 喉の異物感、違和感が続いている
- 痰に血が混じっているが呼吸器内科で異常はないと言われている
- 息苦しさが徐々に出てきた
- 首にしこりが出来てきた
- ヘビースモーカーである
診断、治療
喉頭をしっかり観察するためにファイバースコープを使用し喉の奥を観察します。
腫瘍が確認できた際にはそちらの一部の肉を採取し病理組織診断に提出することで良性悪性の評価を行います(反射が強く出やすい場所のため、必要に応じて麻酔を行います。この検査を行う場合は検査可能な高次医療機関を紹介させていただきます)。
治療は多岐に渡りますが、早期に発見された場合には放射線治療を行うことで95%が寛解に至ることが知られます。いずれにせよ早期診断・早期治療が非常に重要ながんとなります(嗄声というわかりやすい症状が出るため比較的早く見つかることも多い癌です;重要なことは嗄声を放置せずにしっかりと耳鼻科で診てもらうことです。)
上咽頭がん
のど(咽頭)は大きく上・中・下に分けられます。上咽頭は鼻の奥から口蓋垂(のどちんこ)の上の部分を指し鼻からのどへ移行していく部分を言います。上咽頭がんはシンガポール、台湾で高頻度に起こると言われ、日本での発症は人口10万人あたりに0.3人ほどで比較的まれな疾患です。原因はEBウイルスというヘルペスウイルスの一種が原因となる場合と喫煙や過度の飲酒が原因となる場合にわかれ、比較的早期からリンパ節への転移が多いことが特徴と言われます。今まで耳鼻科医として働いている中で、上咽頭に病変がはっきりしない場合でも、リンパ節の腫大がありそちらを調べてみたら上咽頭がんの転移だったケースや大人で咽頭に自覚症状はなかったものの、滲出性中耳炎があり上咽頭を確認してみたら癌が見つかったというケースも多くありました。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- 鼻の症状(鼻詰まり、鼻血が繰り返しでる。)
- 耳の症状(耳が詰まった感じがする、難聴がある)
- 首のしこりがある
診断、治療
診断はファイバースコープを用いてのどの奥を観察することで行います。腫瘍が確認できた場合は組織の一部を摘出し病理検査をすることで診断を確定します。この検査でEBウイルスの関連性についても確認ができますので合わせて評価確認を行います。上記の通り、頸部リンパ節転移を起こしやすい疾患ですので合わせて頸部エコーや頸胸部CTをまた、鼓膜を評価し大人の方が滲出性中耳炎を発症している場合、上咽頭がんの可能性も考慮しファイバースコープによる評価を行うこともあります。
治療は癌の進行度によって異なるため一概には言えませんが、放射線治療に比較的高い親和性をもつため、放射線治療を主体とした治療が標準治療となります。抗がん剤を併用する化学放射線治療を行うケースもありますが、進行状況や本人の全身状態、環境によって様々な治療がありますので主治医によく確認していただくことが望ましいです。
中咽頭がん
中咽頭はのどの真ん中を指し、口を開けた時に見えるのどの奥のあたりから舌根といい舌の根本のあたりを指します。嚥下(飲み込み)や発声に非常に重要な役割を果たします。中咽頭がんはHPVウイルス(ヒトパピローマウイルス)と言って子宮頸がんの原因となるウイルスです。
子宮頸がんワクチンなどでも話題になったものではありますが、同様に中咽頭にも癌を起こすことが知られています。また一方でやはり飲酒、喫煙が原因となるケースもあります。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- のどのつかえ感がある
- 飲み込む時に痛みがある
- 首のしこりがある
診断、治療
診断は口腔内の丁寧な観察(反射がおきますが、触診も行います)および、ファイバースコープを用いて咽頭の観察を行います。腫瘍が確認できた場合は組織の一部を摘出し病理検査をすることで診断を確定します。この検査でHPVウイルスの関連性についても確認ができますので合わせて評価確認を行います。
HPV陽性中咽頭がんの場合、比較的予後は良好(治る見込みが高い)なことが知られ、放射線の感受性も良好なため、腫瘍のサイズや進行状況にもよりますが手術で摘出する場合、放射線治療(抗がん剤を併用する場合もある)を行います。飲酒、喫煙が原因となるHPV陰性中咽頭がんの場合は、治りにくいこともありより侵襲の大きな(身体への負担が大きな)治療が必要となるケースが多いです。
下咽頭がん
下咽頭はのどの一番下、食道につながる部分で前方には喉頭と接する部分になります。飲食物が気管に入らないように喉頭と連動して食物の通過路として機能しています。下咽頭がんは50-70歳代に多いと言われ、男性が女性よりも多い疾患です。やはり飲酒、喫煙が原因となることが非常に多いですが、女性の場合慢性的な貧血などが原因となり発症することもあります。
初発症状がのどのつかえ感やのどの違和感だけということも多く、ファイバースコープでも場合によっては見えにくい位置ということもあり見逃され進行してから耳鼻科に受診されることも実は多い疾患です。重複癌といって食道など上部消化管にも癌が併存しているケースも多くみられます。
こんな症状に心当たりがあればご相談ください。
- のどのつかえ感がある
- 飲み込む時に痛みがある
- のどの違和感が続いている
- 痰が絡んで取れない
診断、治療
診断はファイバースコープを用いてのどの奥を観察することで行いますが見えにくい位置でもあるため、所見によっては息こらえをしたり、体勢を変えたり、首を回すなど様々な方法を用いてのどの奥を観察します。また胃カメラも確認することで腫瘍の範囲や食道への進行状況も合わせて確認を行います。腫瘍は病理組織診断に提出することで良性悪性の評価を行います。
治療は近年医療の進歩に伴い、早期のものに対しては経口からの切除(ロボットによる手術も含む)を行う場合もありますが、進行度によって手術、放射線治療、抗がん剤治療など様々ですので、主治医に確認をください。やはり早期発見・早期治療が非常に重要な疾患ですので、症状が出る場合や、飲酒、喫煙が長い方、多い方は気にして確認をいただければ良いと思います。