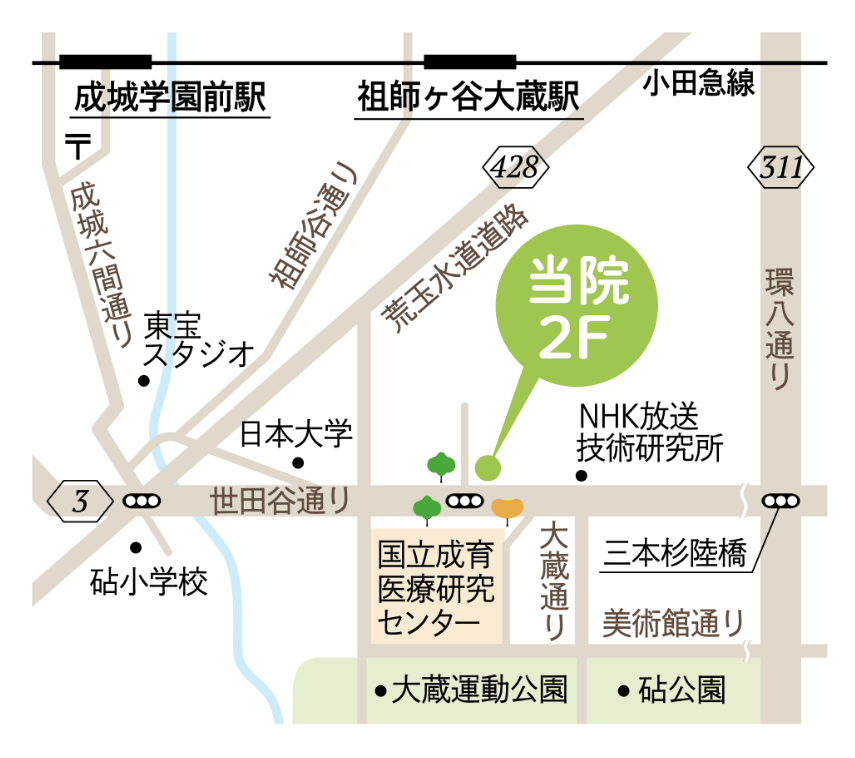嚥下外来とは
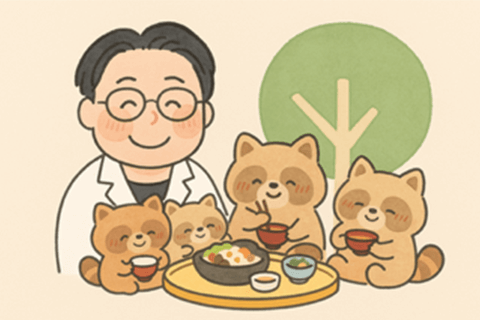
なんとなくのどがイガイガする、痰が絡む、飲食の際にのどの詰まり感があり、むせこむ事が以前と比べて少し多くなった、などといことはありませんか?
年とったな、とそのままにしてしまうこともあるかもしれませんが、放置することで5年後、10年後の誤嚥性肺炎を引き起こす原因にもなりますし、またのどにできる癌など、重篤な疾患が隠れている可能性、はたまた神経疾患が見つかることも一部ですがありえます。
『食べる』ことは当然、生きる上で必須の行為です。美味しいと感じることで、心を満たし、生きる活力や充足感を与えてくれます。飲み込みにくさやむせ込みでお困りの方、また喉の違和感が続いている等自覚されることがある方は是非一度の当院の嚥下外来にご相談ください。
当院での嚥下診療の大まかな流れ
問診
(既往、現在の具体的な症状、飲みやすい飲食物、むせやすい飲食物の確認、内服薬の確認)
診察
- 口内の確認
(舌の動きや萎縮の有無を確認、のどちんこの周りの動きの確認をします) - 頸部(首)の評価
(腫瘍の有無や首の伸展、屈曲についての確認、喉頭挙上の確認) - 全身運動の評価 等
- 口内の確認
検査
内視鏡による評価、嚥下内視鏡検査、(首のエコー検査)
- 内視鏡検査:
(咽頭(いんとう)や喉頭(こうとう)に腫瘍などの明らかな異常病変の有無、声帯の動きの異常の有無を広く確認します。) - 嚥下内視鏡検査(内視鏡検査に合わせて検査実施します):
(着色した水分や食べ物を用いて、飲み込みの状況を内視鏡を使いながら検査を行います:兵頭スコアという点数をつけて嚥下の状況を点数化して確認します) - 首のエコー検査(必要に応じて)首の腫瘍の確認や頚部の重大な異常の評価を行います。
- 内視鏡検査:
検査結果に準じてご本人に最も適切と考えられるリハビリを提案します。
(嚥下障害を引き起こし易い内服薬などもあり、休薬可能なものであれば中止も含めて相談を行うことがあります。)
嚥下障害について
物を食べる(嚥下する)際に、喉や胸のつかえや不快感があり飲み込みがうまくいかなくなることを嚥下障害と言います。
嚥下とは、口の中に入れた食べ物を口の中から食道を通って胃に運ぶ一連の動作のことを言い、少し難しい言葉になりますが、(先行期)、準備期、口腔期、咽頭期、食道期に分けられます。
- 準備期
- 口に入れた食物を、歯で噛んで唾液と混ぜることで飲み込み易い大きさの塊(食塊)を作る過程のこと
- 口腔期
- 咀嚼した食べ物を舌を使って喉の奥に流し込む段階のこと
- 咽頭期
- 口の中で作った食塊を食道に送り込む工程のことで、気管の方に食物が入らないように様々な器官が連動します。この際に気管に入り込んでしまうことが誤嚥です。
- 食道期
- 食塊が食道に送り込まれ、蠕動運動によって胃に運ばれるまでの段階のこと
このどこかにトラブルが起こることで嚥下障害が引き起こされますが、特に多くは口腔期、咽頭期、で障害が起こることが多く、これは主に耳鼻咽喉科・頭頸部外科で扱われる分野になります。
この嚥下動作がうまくいかないことがいわゆる嚥下障害で、食べ物が食道ではなく、気管側に入ってしまうことを誤嚥と言います。
誤嚥の程度や全身状態によって誤嚥性肺炎などの重篤な状況になりえるため、原因となっている疾患の加療や嚥下障害の進行を抑えるため十分なリハビリを行うなど早めの対応が望まれます。
特に誤嚥性肺炎を繰り返すようになると、栄養不良、脱水なども見られるようになりQOL(Quality of life : 生活の質)が下がり、全身の状態も悪循環で徐々に悪くなっていくため、注意が必要です。
嚥下障害で見受けられる主な症状は、以下のものが挙げられます。心当たりのある方は、一度当院にご相談ください。
- 食事の最中にむせる、咳がよく出る
- 食事を食べるのが遅くなり、疲れて食べきれなくなってしまう
- 食後は声がかすれる、ガラガラになる
- 体重がだんだん減少してきている
- 飲み込んだつもりでも口の中に食べ物が残っている
- 喉や胸に何かしらのつかえを感じている
- 微熱が続くようになった など
嚥下障害の原因は多岐に及びますが、加齢、咀嚼機能の低下、唾液腺の委縮や分泌量の低下など、筋力低下をきっかけとしたケースが最も考えられます。他の身体の筋肉同様に喉の周囲の筋肉も加齢とともに低下してきますし、さらに唾液流出の障害などが加わることで嚥下自体が不利になります。この場合は筋力低下を起こさないよう、十分に喉を鍛えていく必要があります。
また、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、神経筋変性疾患(ALS、進行性核上性麻痺など)、代謝性疾患などの病気に罹患し、運動麻痺や筋肉・神経の働きが低下することもあります。また上記以外にも心因性(うつ病 など)や薬剤の影響(抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、抗てんかん薬 など)、外傷、悪性腫瘍(癌)などが原因で起きることもあります。
治療
嚥下障害を引き起こす原因が他にある場合には、まずはそちらの治療を優先します。内服薬などの副作用によって、誤嚥をきたしやすくなる場合もあり、その場合可能なものについては内服の中止や変更などを提案します。
また嚥下障害を改善するためには嚥下リハビリテーションが有用です。リハビリなため、すぐに症状を改善させるといったものではないですが、しっかりと継続することで症状を楽にするというよりも悪化させない。5年後10年後の誤嚥、それに伴った重篤な肺炎を防ぐことを目的にリハビリを行なっていきます。診察所見や嚥下内視鏡検査の結果から患者様それぞれに適したリハビリのやり方を提案していくことが可能です。当院では嚥下に精通した看護師が2名常勤でいてくれるため、看護師から患者さんにリハビリのやり方や改善点などを細かく情報提供できます。
そのほか重度の嚥下障害の場合の場合には外科的な治療を検討することもあります。合併症や手術により喪失する機能もあるため、手術の適応については十分な検討が必要となります。専門施設へご紹介相談をさせていただきます。